|
|
|
|
|
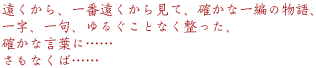 |
|
如月小春について、まるで他人事のように書くなんて無理。 しかし……、一体全体、これはセリフなのだろうか? こういうところに如月小春の才能と異常さが同居している。 つぶやき。言葉。単語。助詞。音。記号。 ひとつの単語、音のなかにあふれるように、物語が沸き立つように、書くこと。語ること。演じること。それが彼女にとっての「一番遠くから見て、確かな一編の物語」だったのでないか? 自分と世界との間に、一枚の薄い(薄さという厚みすらない)フィルターがあって、それを通して、世界を眺めることが、彼女という人間であり、言葉であった。そのフィルターそのものが、彼女であった。そのフィルターのこちら側(観客にとっては向こう側)から、世界を眺める自分は、言語化され、表明される「自分」ではなく、世界とおなじように、他者によって発見されるのを待っている「迷子」だったのでないか、と思ってしまう。そのようにして誰かに「自分」を発見してほしかったのだ。そのようにして、自分=世界であると納得したかったのだ。 だから、如月小春は今も言葉によって、われわれが世界を見るためのフィルターとして、生き続けている……。 |
|